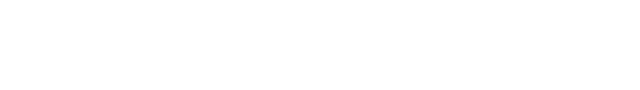気管支喘息
気管支喘息とは
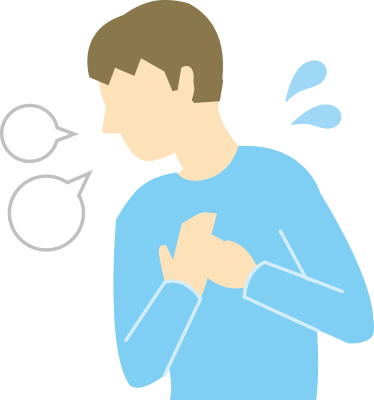 気管支喘息(きかんしぜんそく)は、主にアレルギーなどにより慢性的に気道(気管、気管支)の粘膜が炎症をおこし、狭くなる病気です。呼吸困難の発作や喘鳴(ゼーゼーやヒューヒューと音を立て息苦しくなる状態)、咳などの症状をおこします。
気管支喘息(きかんしぜんそく)は、主にアレルギーなどにより慢性的に気道(気管、気管支)の粘膜が炎症をおこし、狭くなる病気です。呼吸困難の発作や喘鳴(ゼーゼーやヒューヒューと音を立て息苦しくなる状態)、咳などの症状をおこします。
ぜんそくの原因は様々ですが、多くは気管支にアレルギー反応が起きて発症します。その他にも、運動や薬剤が原因となって発症することがあります。成人の場合は原因がわからない非アトピー型が多く、基本的に完治は難しいと考えられています。
喘息の方は症状が無くても気道の炎症や過敏な状態は続いています。そこにかぜなど様座な刺激により気管支が狭くなり症状が出てくることが多いです。
「症状があるときだけお薬を使う、症状がなくなると薬を勝手にやめて病院に行かなくなる」
これを繰り返すと徐々に気道が固くなり、元に戻らなくなる”リモデリング”という状態になり、喘息が重症化してしまいます。これを防ぐためにも医師と相談しながら治療を続けていくことが大事です。
気管支喘息の症状
次のような症状が特徴的です。
- 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、息切れ、咳、胸苦しさの組み合わせが変動してみられる
- 夜間や早朝に症状が悪化する
- 風邪をひいたり、運動後、アレルギー源にさらされたとき、天候の変化、笑う、冷気、強いにおいなどで症状が誘発される
気管支喘息の診断
診断は、特徴的な症状から疑い治療を進めていきます。また必要に応じて呼吸機能検査や血液検査などを行い、他の疾患との鑑別を行います。
喘息治療の目標
増悪因子(アレルギー源、お薬)を避け、最小限の薬物療法により、喘息症状や薬の副作用がなく、日常生活に支障がないようにコントロールし、呼吸機能を維持して増悪や喘息による死亡を防ぐことが目標になります。
喘息治療の治療
喘息の治療薬は大きく長期間管理薬と発作治療薬があります。
長期間管理薬
毎日 使用することで炎症を抑えて発作を予防する薬です。
使用することで炎症を抑えて発作を予防する薬です。
最も重要な薬は吸入ステロイドです。
吸入薬は、細かい薬剤を口から吸う治療法で、懸念されるステロイドの大きな副作用はほぼありません。ただどうしてもお薬が吸入後に口に残るため、副作用(声がれ、カビ)予防のために必ず口すすぎ・うがいが必要です。
そのほか必要に応じて、吸入長時間作用性β2刺激薬、吸入長時間作用性抗コリン薬、抗ロイコトリエン薬、テオフィリン徐放製剤などを併用します。これらの薬を十分に使用しても改善が乏しい重症喘息では、生物学的製剤と呼ばれる注射製剤を使用し治療を行います。
発作治療薬
発作治療薬は気管支を速やかに広げて呼吸を楽にする薬です。
普段の治療を行っていても、何らかの原因で喘息発作が出る時に使用します。発作の時に、吸入短時間作用性β2刺激薬などを頓用で使用したり、普段シムビコートなどを使用している際は発作治療薬として使用することが可能です(維持療法と合わせて1日12回まで)。これらの治療で反応が乏しい場合は、ステロイドの内服治療や点滴を行います。
発作の回数が増える、発作が長引く、発作治療薬を使っても改善しない、などがあるときは速やかに医療機関を受診しましょう。